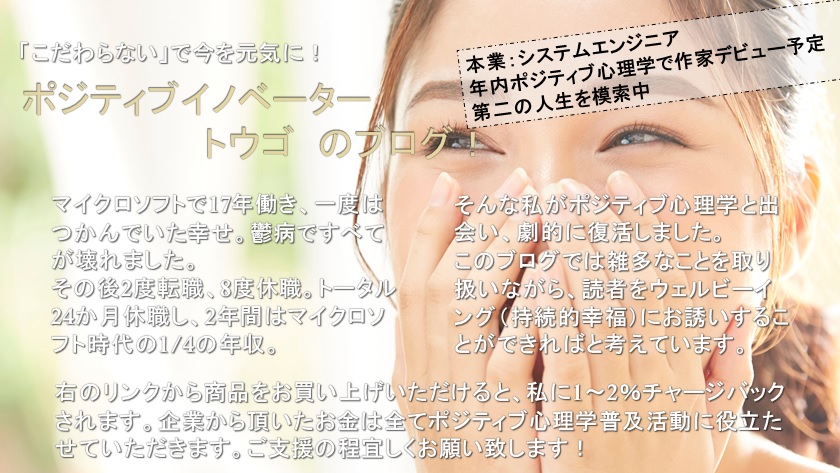今日は「マンガでやさしくわかる傾聴」その2です。

いずみはスマホで傾聴を調べ始める。
最初に目についたスキルは「オウム返し」。
早速実践を始めようとする。
一方で同僚から「役所は変化を嫌う。耳かたむけ課もうさんくさいと思ってる人
達が多く、嫌がらせを受けるかも」と告げられる。
営業開始すると、早速最初のお客が有名なクレーマー。
本来は受付で対応するルールなのだが、これが嫌がらせ第一弾らしい。
オウム返しを続けていると、クレーマーに「ふざけてるのか!」とキレられる。
昼休みの会議室。いずみはふさぎこんでいると、市長がご飯を食べに来た。
「市長のせいでこうなった」愚痴を言ういずみ。たくさん愚痴を言うが傾聴する
市長。自らが落ち着きを取り戻すことで傾聴の凄さを知る。改めていずみは市長
に教えを乞う。
話手は、
・表現したい
・わかってほしい
・受け入れてほしい
と思っているという事。
なので、
・相手に関心を持つ
・受容する
・指示しない
その結果、好感を抱いてもらう事ができ、信頼を構築できる。
具体的には
聞く:
今日は雨だね
雨ですね(言葉のオウム返し)
聴く:
今日は雨だね(あーあ、な雰囲気)
出かけるのがおっくうだよね・・・(感情のオウム返し)
感情のオウム返しが傾聴である、と。
そして大切なのは「共感」。
共感とは話し手の言う事に対して正誤、正邪を判断せず、ただ話を聴いて
あたかも自分が話し手になったかのように想像し、感じ、その感情を味わう事。
このスキルを身に着ける自信がないといういずみに、
「失敗を避けることが最大の失敗だ」「さぁ変化を怖れずやってみよう!」
と励ます市長。
いずみはもう1度トライしよう、と決意するのだった。
---
この市長のレクチャ、これがPCA(来談者中心療法)の肝ですね。
この時点で一致の説明はないけど、
・正誤・正邪を判断せず、相手に関心を持つ(無条件の積極的関心)
・あたかも自分が話し手になったかのように想像し、感じ、その感情を味わう
(共感的理解)
この2つが網羅されています。さらに「感情のバックトラック(オウム返し)」
までここに含まれている。今日これを書いていて「ああ、そういうことか!」
と気づいたのですが、僕は昨今「昭和女子」の傾聴スキルに舌を巻いています。
古宮さんが他の本で「彼女らは自分の家での夕食はメニューが違っても、
「ああ、それいいわね、うちもそれにするわ」と気軽に合わせる。で、もちろん
家では違うメニュー。僕はこれは見かけだけの共感かと思ったのですが、おそら
く、これこそが共感なのだろうなぁと。つまりはその話し手のよその奥さんの
作る料理を想像して、ああ、おいしそー、と思って、そしてその感情を「うち
もそれにする」ここはフィクションだけど、おいしそうという感情を強く表現
する。で、昭和主婦の方々ってこの内容の真実性にあまり興味がなかったのか
なぁとふと思いました。
それと僕はこれまで真実に強くこだわってきたけど、あ、そうか、相手にとって
重要な事でなければ多少フィクションでもいいのか、と。これはすごい気づきに
なるのかもしれません。逆に僕の良さを消す恐れもありますが、とりあえず
「やってみよう」w。
次回その3に続きます。